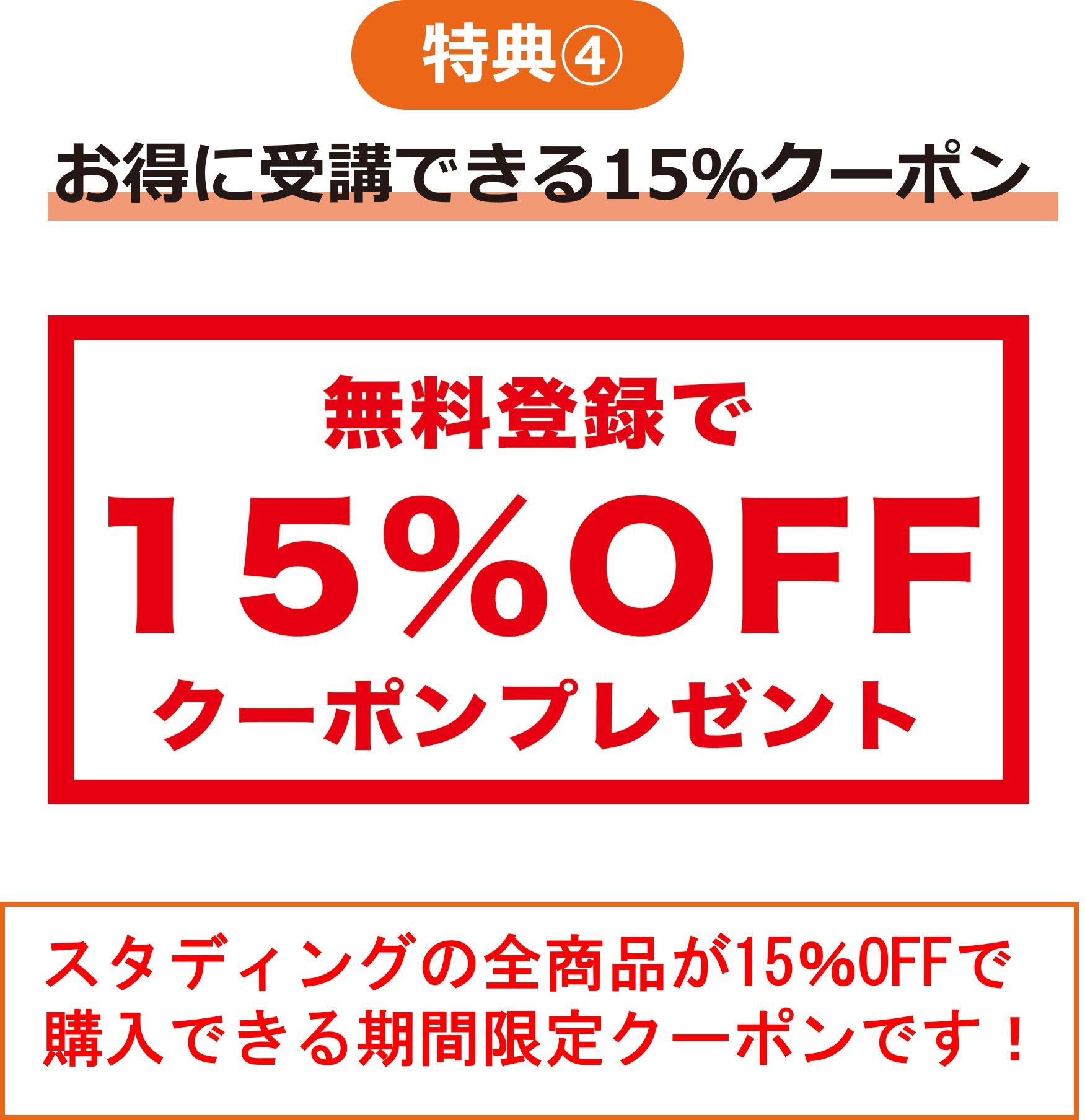弁理士の試験制度
弁理士の試験制度の概要
弁理士試験は、弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です。弁理士試験に合格し、実務修習を修了された方は、「弁理士となる資格」が得られます。
弁理士試験は、筆記試験と口述試験により行い、筆記試験に合格した方でなければ口述試験を受験することはできません。また、筆記試験は短答式と論文式により行い、短答式に合格した方でなければ論文式を受験することはできません。
弁理士試験の内容・日程・合格基準
弁理士試験の概要は以下のとおりです。
| 受験資格 | 特になし (学歴、年齢、国籍等による制限は一切なし) |
|---|---|
| 受験手数料 | 12,000円(特許印紙にて納付) *収入印紙等の特許印紙以外の印紙は受け付けてない。 |
| 試験等の時期 | 令和6年度の実施日程 ●受験願書配布 ・インターネットによる請求 令和6年2月1日(木)~3月22日(金) ・交付場所での交付 令和6年3月7日(木)~4月4日(木) ●短答式筆記試験 令和6年5月19日(日) ●論文式筆記試験 ・必須科目:令和6年6月30日(日) ・選択科目:令和6年7月21日(日) ●口述試験 令和6年10月19日(日)~21日(月) のいずれかの日 |
| 受験地 | ●短答式筆記試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
●論文式筆記試験:東京、大阪 受験地「東京」は東京都の、「大阪」は大阪市の、「仙台」は仙台市の、「名古屋」は名古屋市の、「福岡」は福岡市のそれぞれ近傍を含む。 |
以下、短答試験・論文試験・口述試験それぞれの試験内容や試験時間を紹介します。
■短答試験
| 試験科目及び出題数 | ●特許・実用新案に関する法令※ 20題 ●意匠に関する法令※ 10題 ●商標に関する法令※ 10題 ●工業所有権に関する条約 10題 ●著作権法及び不正競争防止法 10題 全60題 ※出題範囲には、工業所有権に関する条約に関する規定が含まれており、工業所有権法令の範囲内で条約の解釈・判断を考査する。 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式(五肢択一)
ゼロ解答(五肢に加えて「いずれにも該当しない」という選択肢を設けること)は採用しない。 |
| 試験時間 | 3.5時間 |
| 合格基準 | 総合得点の満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。 ただし、科目別の合格基準を下回る科目が一つもないこと。なお、科目別合格基準は各科目の満点の40%を原則とする。近年は39点で一定です。 |
| 問題の公表 | 問題及び解答を、短答式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。 |
■論文試験
論文式筆記試験は、工業所有権に関する法令についての知識を問う【必須科目】と、技術や法律に関する知識を問う【選択科目】により構成されています。
| 試験科目 | 【必須科目】
工業所有権に関する法令
【選択科目】 次に掲げる6科目のうち、受験願書提出時にあらかじめ選択する1科目 なお、選択問題は、受験願書提出時に選択し、その後は変更不可
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 【必須科目】
特許・実用新案:2時間、意匠:1.5時間、商標:1.5時間 【選択科目】 | ||||||||||||||
| 配点比率 | 特許・実用新案: 意匠: 商標: 選択科目は、 2:1:1:1とする。 | ||||||||||||||
| 法文の貸与 | 【必須科目】は、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。 【選択科目】「法律(弁理士の業務に関する法律)」の受験者には、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。 | ||||||||||||||
| 採点について | 必須3科目のうち、1科目でも受験しない場合は、必須科目全ての科目の採点を行わない。 | ||||||||||||||
| 合格基準 | 【必須科目】の合格基準を満たし、かつ【選択科目】の合格基準を満たすこと。 | ||||||||||||||
| 科目合格基準 | 【必須科目】
標準偏差による調整後の各科目の得点の平均(配点比率を勘案して計算)が、54点を基準として口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、47点未満の得点の科目が一つもないこと。 【選択科目】 | ||||||||||||||
| 採点格差の調整 | 必須科目における採点格差の調整は、標準偏差により行う | ||||||||||||||
| 問題等の公表 | 問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する |
■口述試験
| 試験科目 | 工業所有権に関する法令
|
|---|---|
| 試験時間 | 各科目とも10分程度 |
| 試験方法 | 面接方式 受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施する。 |
| 合格基準 | 採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと。 |
| 問題等の公表 | 出題に係るテーマを、口述試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。 解答については、公表しない。 |
弁理士試験の免除制度
弁理士試験では、受験者がすでに試験で考査すべき能力を有していると認められる場合には、申請をすることで一部試験が免除されます。例えば、過去に同試験に合格していたり、特許庁において特定の仕事に一定期間従事していた場合などが該当します。
各試験の免除規定は、以下のとおりです。
■短答式筆記試験の免除について
●短答式筆記試験合格者(平成20年度合格者から適用)
短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、短答式筆記試験の全ての試験科目が免除されます。
●工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方(ただし、平成20年1月以降に進学した方)
大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除されます。
注:事前に短答式筆記試験一部科目免除資格認定の申請を行い、工業所有権審議会の認定を受けることが必要です。
●特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除されます。
■論文式筆記試験(必須科目)の免除について
●論文式筆記試験(必須科目)合格者(平成20年度合格者から適用)
論文式筆記試験の合格発表の日から2年間、論文式筆記試験(必須科目)が免除されます。
●特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
■論文式筆記試験(選択科目)の免除について
●論文式筆記試験(選択科目)合格者(平成20年度合格者から適用)
論文式筆記試験の合格発表の日から永続的に論文式筆記試験(選択科目)が免除されます。
●修士又は博士の学位を有する方*
論文式筆記試験(選択科目)の「科目」に関する研究により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する方のうち、学位授与に係る論文の審査に合格した方は、論文式筆記試験(選択科目)が免除されます。
●専門職の学位を有する方*
論文式筆記試験(選択科目)の「科目」に関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣が定める学位を有する方のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文(前記単位には含まない)の審査に合格した方は、論文式筆記試験(選択科目)が免除されます。
●公的資格を有する方
弁理士法施行規則で定める公的資格者(技術士、一級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、薬剤師、情報処理技術者、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士)については、各資格に対応する論文式筆記試験(選択科目)が免除されます。
*修士・博士・専門職学位を有する方については、事前に選択科目免除資格認定の申請を行い、工業所有権審議会の認定を受けることが必要です。
■口述試験の免除
特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
※以上、特許庁のホームページより抜粋