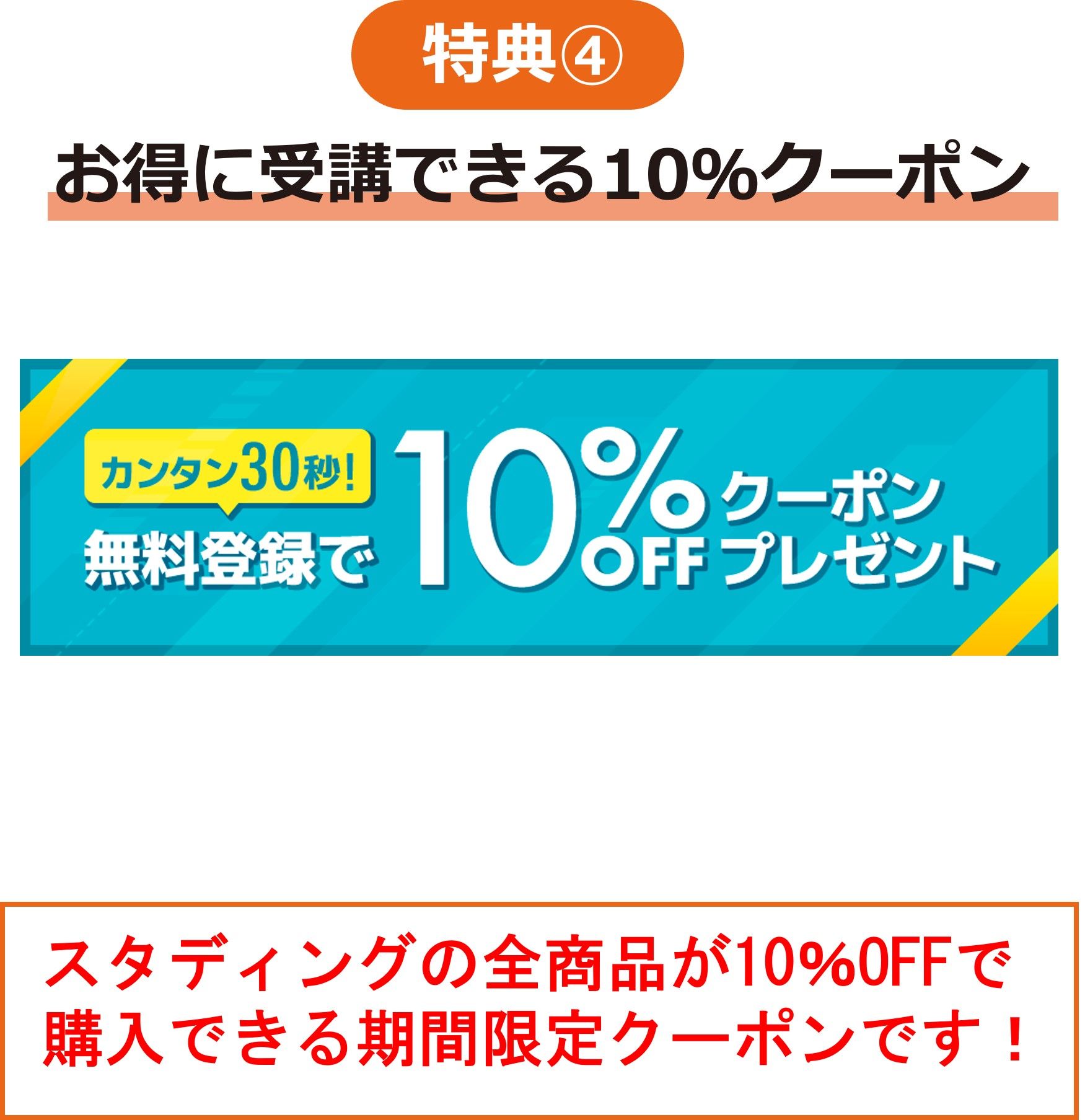2025年度(令和7年度)弁理士試験の試験日程・試験会場・合格発表スケジュール
本記事では、2025年度(令和7年度)の弁理士試験の試験日程から、試験会場、合格発表のスケジュール、申し込み方法までまとめて紹介します。
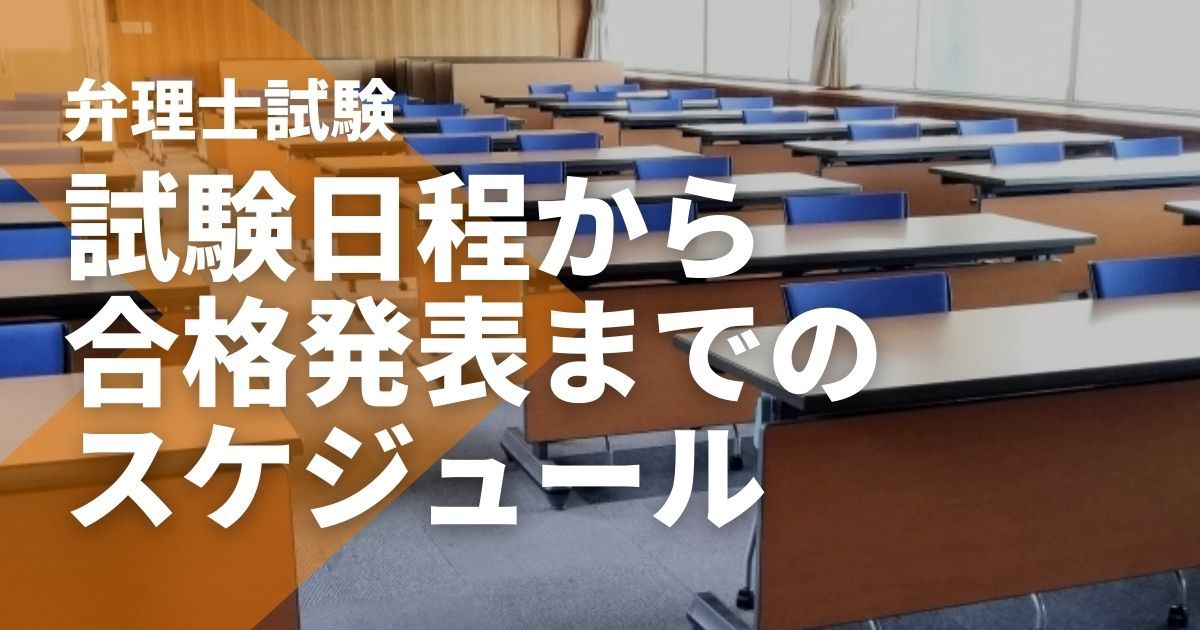
【目次】
・2025年度(令和7年度)弁理士試験の試験日程・合格発表はいつ?
・弁理士試験の申し込み方法は?注意点とあわせて解説
・2025年度(令和7年度)弁理士試験の試験内容・試験会場
・弁理士試験の合格率は?
・弁理士試験は独学でも合格可能?
・まとめ
2025年度(令和7年度)弁理士試験の試験日程・合格発表はいつ?
弁理士試験は年に一度実施されており、ある程度時期は決まっています。2025年度(令和7年度)の弁理士試験の試験日程・合格発表スケジュールは以下の通りです。
弁理士の試験日程と合格発表・短答式試験:5月18日(日)
・論文式試験(必須科目):6月29日(日) ・論文式試験(選択科目):7月27日(日) ・口述試験:10月18日(土)~20日(月) ・最終合格発表:11月10日(月)予定 |
弁理士試験はまず短答式試験を受験し、合格すれば論文式試験、さらに口述試験と進む形式になっています。
令和7年度願書の交付・請求、受付
●願書交付・請求期間
- インターネットによる請求:令和7年2月3日(月)~3月21日(金)
- 交付場所での交付:令和7年3月3日(月)~3月31日(月)
- 郵送による請求:令和7年3月3日(月)~3月21日(金)
●願書受付期間
- 令和7年3月6日(木)~4月3日(木) ※4月3日消印有効
令和7年度試験実施日程
■短答式筆記試験
- 令和7年5月18日(日)
※短答式合格発表:令和7年6月9日(月)予定
■論文式筆記試験
- 必須科目:令和7年6月29日(日)
- 選択科目:令和7年7月27日(日)
※論文式合格発表:令和7年9月24日(水)予定
■口述試験
- 令和7年10月18日(土)~20日(月)
※最終合格発表:令和7年11月10日(月)予定
例年の弁理士試験日程は?【2026年度以降はどうなる?】
例年の弁理士試験のスケジュールは以下の通りとなっています。
- 受験願書の提出:3月中旬〜4月上旬
- 受験票の発送:5月上旬~中旬頃
- 短答式筆記試験:5月中旬~下旬
- 論文式筆記試験(必須科目):6月下旬~7月上旬
- 論文式筆記試験(選択科目):6月下旬~7月上旬
- 口述試験:10月中旬~下旬
- 最終合格発表:10月下旬~11月上旬頃
- 合格証書発送:11月上旬頃
スケジュールが発表されている令和6年度実施分まで、近年は上記のスケジュールに則っています。2026年度(令和8年度)以降はまだ発表されていませんが、同様のスケジュールとなる可能性が高いでしょう。
ただし、毎年1月中旬に官報で公告される正式な日程は必ず確認するようにしましょう。
弁理士試験の申し込み方法は?注意点とあわせて解説
弁理士試験を受験するためにはまず、申し込みが必要です。いくつかの申し込み方法がありますが、それぞれ期限が決められているため、締切に遅れないよう注意しましょう。
受験願書の請求方法
弁理士試験の申し込みで最初のステップは受験願書の請求です。具体的には、以下3つの請求方法があります。
- インターネット
- 郵送
- 直接交付
▼インターネット
弁理士試験の受験願書は、インターネット経由で請求できるようになっています。公式サイトの専用ページにアクセスし、メールアドレスやパスワードなどを設定し、願書請求の必要事項を入力します。受付確認のメールを受信したら手続きは完了です。
インターネットで願書を申し込んだ場合、受験願書は3月3日以降、順次送付されます。
令和7年度試験のインターネットによる願書請求の期間は令和7年2月3日(月)~3月21日(金)です。インターネット経由で簡単に請求できるうえ、ほかの請求方法よりも早く受付が開始されるため、忘れないうちに願書を請求したい方にはインターネット経由がおすすめです。
▼郵送
郵送で願書請求を行なう場合は、封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と朱書したうえで、送付先住所を記載した角形2号(240mm×332mm)の返信用封筒を同封して郵送します。宛先は「郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁秘書課弁理士室試験第一班」で、返信用封筒の切手は不要です。
令和7年度試験の郵送による願書請求の期間は令和7年3月3日(月)~3月21日(金)です。3月21日必着であるため注意しましょう。
▼直接交付
受験願書の直接交付を受ける場合は、特許庁や日本弁理士会、各経済産業局知的財産室などを訪問することになります。すべての都道府県に交付場所があるわけではないため注意しましょう。具体的には、東京のほか、北海道、宮城、埼玉、愛知、大阪、広島、香川、福岡、沖縄の各庁舎が挙げられています。
令和7年度試験の直接交付による願書請求の期間は令和7年3月3日(月)~3月31日(月)です。しかし、行政機関の休日などを除いた午前9時~午後5時が対象となっているため注意しましょう。また、場所によっては「正午~午後1時」を除くとしている場合もあります。
入館の際には身分証明書を求められることもあるため、用意しておきましょう。
受験願書の提出方法
受験願書の交付時には、提出用の専用封筒も送られてきます。その封筒を使い、必要な書類と一緒に簡易書留(推奨)で郵送してください。提出時に必要な書類は以下の通りです。
- 受験願書(交付されたもの)
- 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、願書に貼り付け)
- 12,000円分の特許印紙(願書に貼り付け)
- 免除を受けるための証明書類
受験願書を記入したら、写真と印紙を貼り付けます。弁理士試験においては、一部試験に免除制度が設けられています。免除の対象となる場合は、証明書類の同封も忘れないようにしましょう。
関連記事:弁理士試験に受験資格はある?免除制度があるって本当?
令和7年度試験における受験願書の受付期間は令和7年3月6日(木)~4月3日(木)です。4月3日消印有効となっていますが、年に一度の試験であるため、万が一に備えて早めに提出を済ませておきましょう。
申し込み時の注意点
願書の請求方法は3つありますが、受取および提出は必ず郵送となる点に注意しましょう。インターネットのように瞬時に送受信が完了するわけではないため、ある程度日数に余裕を持って対応することをおすすめします。
また、一部試験の免除を受ける場合は願書への同封を忘れないようにしてください。さらに、願書に貼り付ける印紙が「特許印紙」である点にも注意しておきましょう。使用機会の多い「収入印紙」とは異なります。特許印紙は全国の集配郵便局や特許庁などで購入可能ですが、取り扱っていない場合もあるため事前に電話などで確認しておくと安心です。
2025年度(令和7年度)弁理士試験の試験内容・試験会場
ここでは令和7年度弁理士試験について、試験形式別の試験科目や試験時間、試験会場などについて紹介します。
◆短答試験
●試験科目・試験時間・合格基準ほか
| 試験科目
及び出題数 | ●特許・実用新案に関する法令※ 20題 ●意匠に関する法令※ 10題 ●商標に関する法令※ 10題 ●工業所有権に関する条約 10題 ●著作権法及び不正競争防止法 10題 全60題 ※出題範囲には、工業所有権に関する条約に関する規定が含まれており、工業所有権法令の範囲内で条約の解釈・判断を考査する。 |
| 出題形式 | マークシート方式(五肢択一) ゼロ解答(五肢に加えて「いずれにも該当しない」という選択肢を設けること)は採用しない。 |
| 試験時間 | 3.5時間 |
| 合格基準 | 総合得点の満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、科目別の合格基準を下回る科目が一つもないこと。なお、科目別合格基準は各科目の満点の40%を原則とする。近年は39点で一定です。 |
| 問題の公表 | 問題及び解答を、短答式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。 |
●試験会場
短答式試験の会場は「東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡」とされています。大学などで実施されることが多く、令和6年度試験の会場は以下の通りでした。
- 東京:立教大学池袋キャンパス
- 大阪:関西大学千里山キャンパス
- 仙台:学校法人北杜学園 仙台大原簿記情報公務員専門学校
- 名古屋:名古屋市立大学滝子キャンパス
- 福岡:福岡工業大学
※上記は令和6年度試験の会場なのでご注意ください。
令和7年度の会場は4月中に官報で公告される予定となっています。
◆論文試験
●試験科目・試験時間・合格基準ほか
論文式筆記試験は、工業所有権に関する法令についての知識を問う【必須科目】と、技術や法律に関する知識を問う【選択科目】により構成されています。
| 試験科目 | 【必須科目】
工業所有権に関する法令
| ||||||||||||||
| 試験時間 | 【必須科目】 特許・実用新案:**2時間**、意匠:**1.5時間**、商標:**1.5時間** 【選択科目】 **1.5時間** | ||||||||||||||
| 配点比率 | 特許・実用新案: 意匠: 商標: 選択科目は、 **2:1:1:1**とする。 | ||||||||||||||
| 法文の貸与 | 【必須科目】は、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。 【選択科目】「法律(弁理士の業務に関する法律)」の受験者には、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。 | ||||||||||||||
| 採点について | 必須3科目のうち、1科目でも受験しない場合は、必須科目全ての科目の採点を行わない。 | ||||||||||||||
| 合格基準 | 【必須科目】の合格基準を満たし、かつ【選択科目】の合格基準を満たすこと。 | ||||||||||||||
| 科目合格基準 | 【必須科目】 標準偏差による調整後の各科目の得点の平均(配点比率を勘案して計算)が、**54点を基準**として口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、**47点未満の得点の科目が一つもないこと。** 【選択科目】 科目の得点(素点)が**満点の60%以上**であること。 | ||||||||||||||
| 採点格差の調整 | 必須科目における採点格差の調整は、標準偏差により行う | ||||||||||||||
| 問題等の公表 | 問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する |
●試験会場
論文式筆記試験の会場は「東京及び大阪」となっています。令和6年度試験の会場は以下の通りでした。
▼論文式筆記試験(必須科目)
- 東京:立教大学池袋キャンパス
- 大阪:関西大学千里山キャンパス
▼論文式筆記試験(選択科目)
- 東京:東京富士大学
- 大阪:関西大学千里山キャンパス
※上記は令和6年度試験の会場なのでご注意ください。
令和7年度の会場は4月中に官報で公告される予定となっています。
◆口述試験
●試験科目・試験時間・合格基準ほか
| 試験科目 | 工業所有権に関する法令
|
| 試験時間 | 各科目とも10分程度 |
| 試験方法 | 面接方式
受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施する。 |
| 合格基準 | 採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと。 |
| 問題等の公表 | 出題に係るテーマを、口述試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
解答については、公表しない。 |
●試験会場
口述試験の試験会場は「東京」のみです。令和6年度試験の会場は以下の通りでした。
- ザ・プリンスパークタワー東京
※上記は令和6年度試験の会場なのでご注意ください。
令和7年度の会場は4月中に官報で公告される予定となっています。
※スタディングでは、願書の配布、受験申請の手続き代行などは行なっておりません。受験に関する申請などは、各自お願いいたします。
弁理士試験の合格率は?
弁理士試験の合格率は例年6〜10%程度で推移しています。ほかの国家資格と比較しても合格率は低く、難関試験の1つであるといえます。特に平成26年度以降は一度も合格率10%を越えていません。直近の令和6年度では6.0%とかなり低くなっています。
合格率=試験難易度というわけではありませんが、簡単に合格できる試験ではないためしっかりとした勉強・対策が求められます。
関連記事:弁理士資格の試験難易度・合格率は?他資格との比較や合格者の特徴も解説!
弁理士試験は独学でも合格可能?
弁理士試験合格のためには、一般的に3000時間程度の勉強が必要とされています。さらに、試験の形式も短答式試験・論文式試験・口述試験と分かれていることから、計画的に対策を進める必要があります。特に論文式試験や口述試験は自己評価が難しいため、独学での対策は難易度が高いでしょう。
もちろん、弁理士試験に独学で合格することが不可能というわけではありません。しかし、短期間で着実に合格を目指すのであれば、通信やオンラインの講座を利用したり、スクールに通ったりするのがおすすめです。
関連記事:弁理士試験の独学合格は難しい?何年かかるかやメリット・デメリットを解説
まとめ
本記事では、弁理士試験の概要や日程、申し込み方法などについて詳しく紹介しました。ポイントは以下の通りです。
- 弁理士試験は年に1度実施される
- 短答式試験・論文式試験・口述試験に分かれている
- 弁理士試験の願書請求方法はインターネット・郵送・直接交付の3種類
- 弁理士試験の願書提出は郵送のみ
- 弁理士試験の合格率は6〜10%程度と低く、計画的な学習が必要