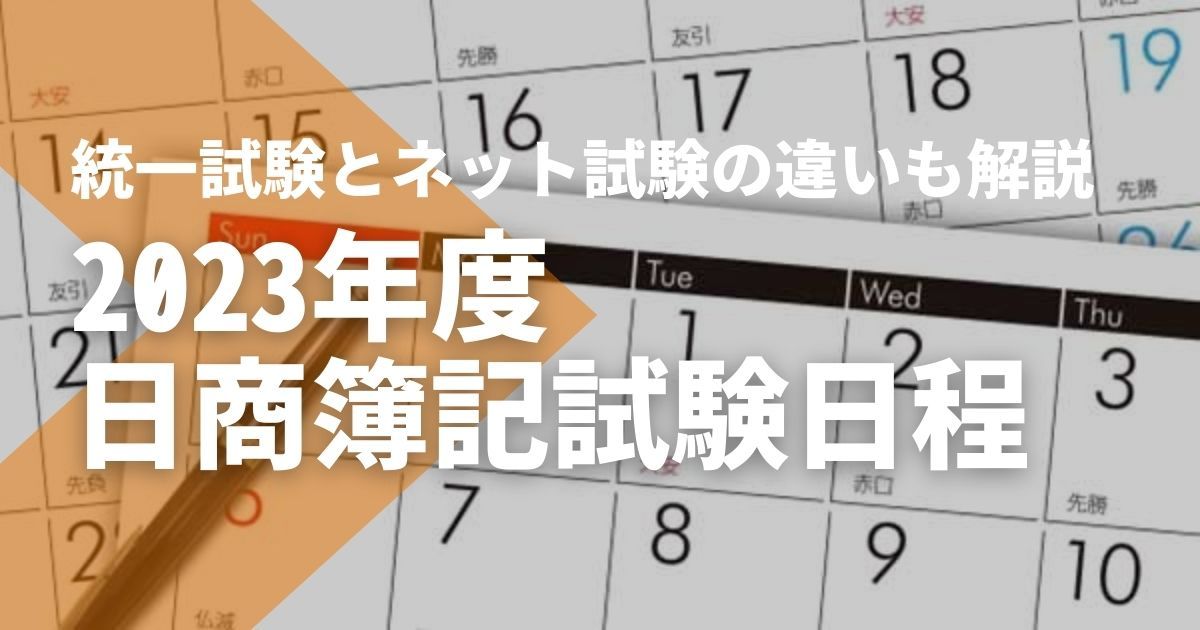2023年「資格別ランキング」TOP10
はじめに2023年(1月1日~12月20日で集計)に読まれた全コラム系記事のアクセス数を合計し、資格ごとにまとめたランキングがこちらです。
※各資格の「人気記事一覧」から、アクセスが多かった記事の一覧へジャンプできます。
受験者数が多い宅建士や簿記、FPが上位に入る一方で、司法試験、税理士、社労士、中小企業診断士などの難関資格もランクインしています。
中でも今年は税理士と社労士が大きく数字を伸ばしています。
資格別「2023年人気記事」紹介
続いて、ランキング上位の資格ごとに、2023年に読まれた記事をそれぞれ3つずつご紹介します。
宅建士(宅地建物取引士)

| 近年の宅建の合格率や、合格ラインとなる点数を解説。
また、受験申し込みから合格後までの一連の流れや、合格発表の確認方法など、宅建を受験する際に知っておきたいことをわかりやすく紹介していきます。
|

| 申し込みから試験日、合格発表まで、主なスケジュールを紹介。
例年7月上旬から宅建試験の試験案内が配布されます。郵送、またはインターネットで申し込むことができます。
|

| 宅建士試験の通称「5点免除(5問免除)」制度とは?
例年、5点免除制度の利用者は一般の受験者より合格率が高くなっています。制度を利用するための条件、申し込み方法、いつまでに申し込むべきかなどについて解説します。
|
簿記
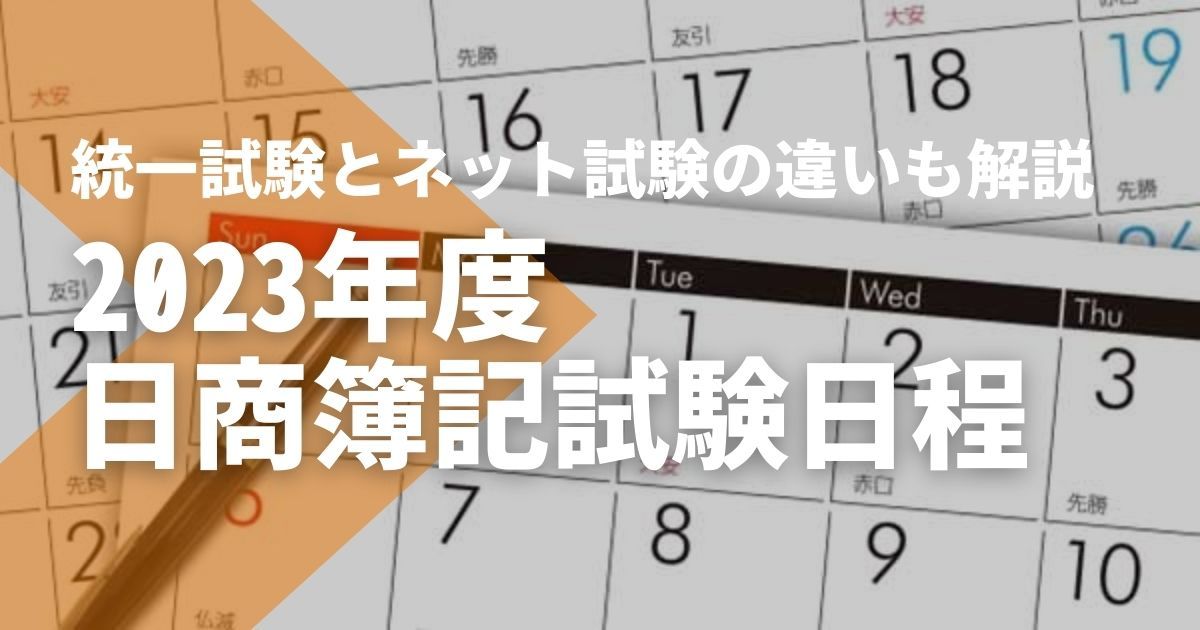
| 日商簿記の統一試験の日程を中心に解説しています。
なお、「ネット試験」は、統一試験とは違って明確な試験日が設定されておらず、各地のテストセンターで随時実施されています。
|

| 複数の団体で実施されている簿記試験。各団体の違いとは?
日商簿記・全商簿記・全経簿記それぞれの特徴や難易度、取得のメリットを紹介します。
|

| 日商簿記各級の合格までに必要な勉強時間を紹介します。
また、難易度、合格率、合格に向けた各級のポイントも解説しています。
|
公務員

| 公務員試験の日程を国・自治体別にご紹介しています。
試験日程ごとに自治体の採用ページのリンクを掲載。
|

| 公務員の副業は原則禁止ですが、近年は見直す動きも?
公務員の副業が禁止されている理由や、全国各地でさまざまな副業が解禁された事例、そして副業として認められる事例・認められない事例について解説します。
|

| 市役所職員の仕事内容を職種別に解説しています。
とある市役所の「子育て支援課」に勤務する職員Aさん(28歳・女性・公務員歴6年)の1日の流れも紹介。
|
行政書士

| 行政書士試験を独学で合格するポイントを解説しています。
近年、行政書士試験の難易度は高くなりつつありますが、しっかりと対策を行うことで独学でも十分に合格することは可能です。
|

| 行政書士試験に合格してから登録しないとどうなる?
行政書士は試験に合格したらすぐに業務を行えるわけではなく、行政書士登録を行う必要があります。
この記事では行政書士試験に合格してから登録しないとどうなるのか、登録するメリットや登録の流れについて解説します。
|

| 行政書士として独立するために必要な資金や手続きを解説します。
行政書士は独立開業しやすい資格のひとつですが、メリット・デメリットに加え、人によっては向き不向きもあります。そのため、独立を考えているのであればその両方を頭に入れた上で入念な準備をすることが大切です。
|
司法試験/予備試験

| 資格試験の最高峰ともいえる司法試験。その難易度を解説します。
また、司法試験を受験するための資格を得る方法の1つである予備試験についても合わせて解説しています。
|

| どの法科大学院が実績を出している?ランキング形式で紹介。
また、司法試験を受けるための2つのルートについても解説します。
|

| 司法試験の受験回数制限について詳しく解説します。
制度の内容や受験回数別の合格者の分布、万が一5回とも不合格になってしまった場合の対応策について解説しています。
|
税理士

| 5科目の合格を目指す税理士試験。短期合格するためには?
この記事では、税理士試験の科目別勉強時間や2〜3年で合格を目指す受験プラン例を紹介しています。
|

| 税理士試験には科目免除制度があります。
税理士を目指している受験者の多くははじめから5科目すべてを受験するつもりがなく、試験の全部又は一部の免除制度を利用するという方が増えています。
この記事では要件などを解説します。
|

| 2023年に緩和された税理士の受験資格について解説します。
税理士の受験資格や要件を満たす方法、税理士になるための方法について解説します。
|
FP

| FPは2級から受けることもできますが受験資格があります。
3級を飛ばしていきなり2級からチャレンジするには、日本FP協会が実施するAFP認定研修を受講するか、同協会が定義する実務経験を2年以上有している必要があります。
|

| FP技能検定の基本情報を解説します。
スタンダードである「FP技能士」の1級・2級・3級はすべて国家資格です。FP技能検定は、日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)という2つの実施機関によりそれぞれ行われますが、いずれを受検して合格しても国家資格としての価値を持ちます。
|

| FP試験の近年の合格率をもとに、各級の難易度を解説します。
2~3級であれば、国家試験の中では合格しやすい試験です。ただし、1級になると、特に学科試験の難易度が高くなります。
|
建築士

| 建築士試験の受験資格について解説しています。
また、建築士の資格の取得方法や実務経験、難易度、合格のコツについてもまとめています。
|

| 建築士になるための基本情報を解説しています。
一級、二級建築士試験は受験資格がそれぞれ異なります。建築士になるまでの流れや受験資格などについてご紹介します。
|

| 社会人から建築士を目指す場合に必要な要件などを解説します。
建築分野に無縁だった社会人がさまざまな方法で資格取得に挑戦しています。社会人が建築士の受験資格を得るための条件や仕事と両立できる勉強方法をご紹介します。
|
社労士(社会保険労務士)

| 社労士試験の難易度とは?どれくらい難しいかを解説します。
この記事では、司法書士、行政書士、宅建士といった他の国家資格と比較し、合格率、勉強時間、試験内容などの観点から難易度を考えます。
|

| 「社労士」と「労務管理士」の2つの資格の違いを解説します。
名前は似ていますが、仕事内容や資格取得方法などはまったく異なります。社労士にしかできない業務もあります。この記事ではそれぞれの資格について詳しく紹介します。
|

| 社労士試験の日程や、試験の基本情報をご紹介しています。
試験の主なスケジュールや、当日の時間割など、社労士試験に関する情報をまとめています。
|
中小企業診断士

| 中小企業診断士試験の免除制度について詳しく解説しています。
上手く活用すれば負担を軽減しながら中小企業診断士の資格を取得できるでしょう。
|

| 中小企業診断士試験の養成課程について紹介します。
養成課程の内容やカリキュラム、実施機関の紹介のほか、働きながら受講できるのか、費用はいくらかかるのかなども解説します。
|

| 中小企業診断士試験の難易度はどれくらい?
中小企業診断士試験は、科目数が多く、合格率も低い傾向にあります。この記事では、難易度や合格までの勉強時間、効率的に合格するための方法などを解説します。
|
2024年も資格合格を目指す方々を応援します!
スタディングでは、これからも資格合格パートナーとして、資格や試験、キャリアに関する情報を発信していきます。
「自分のスキルを生かせる資格を見つけたい」「合格のためのポイントを知りたい」「資格をとった先でどんなキャリアがあるのか知りたい」など、資格に関する疑問があったら、ぜひスタディングをのぞいてみてください。きっと答えやヒントが見つかるはずです。
また、スタディングではすべての講座で「無料お試し」をご提供しています。
「この資格が気になる……」と思ったら、ぜひスタディングで体験してみてください。
2024年もスタディングをよろしくお願いいたします。