令和7年度(2025年度) 司法書士試験 総評と令和8年度(2026年度)の対策
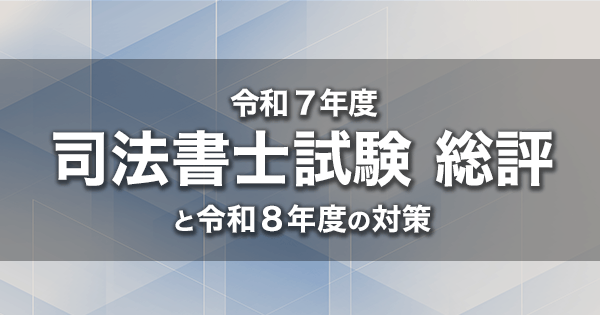
主任講師 山田 巨樹
1.午前多肢択一式
(1)憲法(第1問~第3問)
憲法は、いずれも難易度の高い問題でした。第1問は外国人の人権に関する判例からの出題でした。肢ア、肢イ、肢ウは、基本講座でも紹介させていただいている基本的な判例ですので、これらから正解を導けたのではないかと思います。第2問は政党に関する判例からの出題でした。政党に関する出題ですが、正解肢である肢エは基本講座の司法権で紹介させていただいている判例の知識です。もう一つの正解肢である肢アですが、模擬試験の第3問で出題させていただいている知識です。模擬試験の復習をされていた方は正誤の判断ができたと思います。第3問は、肢ウと肢エの正誤の判断ができれば正解を導けたと思いますが、少し細かな判例の知識なので、間違っても仕方ないと思います。
(2)民法(第4問~第23問)
(3)刑法(第24問~第26問)
刑法については、いずれの問題も例年に比べて難易度が高かったように感じました。この3問のうち1問でも正解できれば十分だったのではないかと思います。
(4)会社法・商法(第27問~第35問)
第27問~第34問が会社法からの出題でしたが、概ね、基本的な条文の知識をもとに解ける問題が中心でした。第35問の商法は、令和2年度に出題されたばかりの匿名組合から出題でした。過去問を通して知識を整理していた方は対応できたのではないかと思います。
(5)まとめ
今年度の午前の部については、昨年と比べて憲法と刑法が難しく感じられた方が多かったのではないかと思います。また、民法についても、昨年より少し難易度が高い問題が含まれていた印象です。そのため、今年度の午前の部の基準点は、昨年度より少し低くなる可能性があるのではないかと予想されます。
毎年お伝えしていることではありますが、司法書士試験では、過去の試験で出題された知識以外の内容が出題されることもあります。その場合、合格レベルにある受験生でも得点することは難しいです。重要なのは、過去の司法書士試験で出題されている知識を正確かつ横断的に身につけているかどうかです。令和7年度の司法書士試験の合格を目指して勉強をしてきた方の中には、試験直前期である5~6月を過ごして「多くのことをこなすことはできない」と感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?こなすことができるのは、過去の司法書士試験で出題されている知識と講義で紹介された改正で加わった知識程度だと思います。勉強をしていると、細かな知識が気になるところかと思いますが、まずは過去の試験で出題された知識を正確に覚え、横断的な整理を行うことが大切です。
2.午後多肢択一式
(1)民事訴訟法(第1問~第5問)・民事保全法(第6問)・民事執行法(第7問)
民事訴訟法は、昨年と同様、基本的な知識で正解を導くことができる問題が中心でした。ただし、第4問はやや難しいと感じた方もいらっしゃったかもしれません。
第6問の民事保全法と第7問の民事執行法については、基本的な知識を正確に覚えておけば、選択肢の組み合わせから正解を導くことができたのではないかと思います。
(2)司法書士法(第8問)・供託法(第9問~第11問)
司法書士法は、基本的な知識からの出題でした。一方、供託法は、例年よりやや難易度が高かった印象です。特に第10問については、正解を導くのが難しかった方も多かったのではないでしょうか。
(3)不動産登記法(第12問~第27問)
(4)商業登記法(第28問~第35問)
商業登記法については、第28問を除き、例年と同レベルの難易度だったと思います。過去問の知識と会社法の基礎知識で正解を導ける問題がかった印象です。
商業登記法の多肢択一式で必要とされる知識は、記述式の対策で身につく内容も多いです。そのため、記述式の学習を進める中で知識を整理し、択一式にも対応できる力を養っていくことが重要です。また、商業登記法の学習を進める際には、会社法の知識が基礎となるため、商業登記法の勉強と並行して、該当箇所の会社法の学習を進めていただければと思います。
(5)まとめ
午後の部につきましては、全体的には昨年よりやや難易度が高かった印象です。そのため、午前の部と同様、合格基準点は昨年よりは下がると思われます。
午後の部の民事訴訟法から供託法の対策ですが、出題数があまり多くないことから、多くの時間をかけて勉強することはできないと思います。そのため、過去に出題されている知識をしっかりと覚えるという作業に徹していただければと思います。
午後の部の不動産登記法および商業登記法の多肢択一式については、いきなり細かな先例を覚えていくのは得策ではありません。まずは、記述式の学習を通じて、不動産登記法及び商業登記法の基本的な仕組みを理解し、基本的な知識を身につけることが大切です。その後、基本的な仕組みの理解と知識が身につけば、細かな先例も覚えやすくなっていますし、知らない先例が出た場合も、解答を導き出せる場合も増えてくるからです。
スタディングの受講生の方におかれましては、スマート問題(一問一答)とセレクト過去問を繰り返し解き、解説までしっかりと覚えることを目指してください。この作業を徹底することで、過去に出題されている知識はしっかりと身に付きます。そして、このレベルに到達すれば、自分に不足している部分が自然と見えてくるはずですので、各自で足りない部分の学習を進めていけば大丈夫です。
3.記述式
(1)不動産登記法
記述式の問題については、皆様それぞれに解答手順を確立されているかと思います。
私の場合、以下の手順で解答を進めています。
- 問1~問3を読む
- 設例1と設例2を読み、各問との対応関係を確認する
- 答案用紙のチェック
- (答案作成にあたっての注意事項)の確認
- 別紙1と別紙5-1、別紙5-2の登記事項証明書の確認
これらをさっと行った後、設例で示された別紙を確認しつつ、解答を作成していきます。この手順は、毎年変わりません。では、各設問を簡単にですが、検討していきたいと思います。この手順は、毎年変わりません。
問1は、登記済証を紛失してしまった場合の代替手段が問われています。過去に多肢択一式や記述式でも多く問われている知識です。
問2は、令和7年7月4日に申請した登記の申請情報が問われています。記述式で仮登記が問われたのは、初めてではないでしょうか?仮登記の本登記、事前に住所変更の登記をすること自体は難しくなかったと思います。問題は、本登記の前提として相続登記を入れるか否かです。ここは、不動産登記法の択一の平成15年第21問肢3、平成26年第20問肢アで出題されている先例の知識から考えて、相続登記は不要と判断した方が多かったのではないかと思います。そして、(答案作成に当たっての注意事項)5(3)で「申請件数及び登録免許税の額が最も少なくなるように登記を申請する。」と指示がありましたので、相続登記を申請しないということになろうかと思います。もっとも、相続登記を入れてしまっても、大きな減点にはならないのではとも思います。なぜなら、却下事由には該当しないからです。
問3は、乙土地について令和7年7月4日に申請した登記の申請情報が問われています。実務でもあまり目にすることない登記手続のオンパレードでした。
問題文を見る限り、
1. 2番付記1号抵当権の債権質入抹消
2. 1番賃借権移転
3. 2番抵当権移転
をしなければならないことは気づけたのではないかと思います。
しかし、「1.2番付記1号抵当権の債権質入抹消」の申請情報の書き方を学習していた方は、まずいらっしゃらなかったのではないかと思います。この辺りは、抹消しなければならないということに気づき、抹消登記の形の申請情報を書けていればいいのではないかと思いました。
(2)商業登記法
商業登記法についても、不動産登記法と同様に、皆様それぞれに解答手順を確立されているかと思います。私の場合、以下の手順で進めています。
- 問1~問5を読む
- 第37問の最初に書かれている問題文を読む
- 答案用紙のチェック
- (答案作成にあたっての注意事項)の確認
- 別紙11の会社の登記記録を確認
これらを行った後、各問で示されている資料を確認しながら解答を仕上げていきます。 問2と問4で「登記することができない事項」が問われていますので、「登記することができない事項」があることを前提に資料を読んでいく必要があります。
問2では、「別紙7の第2号議案 取締役選任の件」が「登記することができない事項」だったわけですが、詳細は説明は割愛させていただきますが、難易度が高かったと思います。
問4では、「別紙9の第2号議案 支配人選任の件」が「登記することができない事項」だったわけですが、こちらは監査等委員会設置会社の設定がなされていることから、支配人の選任を取締役に委任することはできず(会社法399条の13第4項第3号)、重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款変更決議が必要点を判断できたかがポイントだったように思います。
もっとも、検討することが多いため、ここまでたどり着かなかった方もいたかと思います。
(3)まとめ
まず、今年度の記述式の問題は、不動産登記法と商業登記法共に難しかったということです。個人的な感想としましては、受験生の実力を適正に図る出題とはいえなかったのではないかということです。このような出題がなされてしまうと、記述式ではあまり差が出ずに、結局、択一勝負になってしまうのではないかと思いました。
次年度以降の対策ですが、今年のような出題に備えて学習する必要はありません。今年度のようなイレギュラーな出題がなされた場合、他の受験生も解けません。大事なのは、基本的なオーソドックスな出題がされたときに取りこぼさないことです。
そのために、毎年お伝えしておりますが、まずは、設例を通して基本的な雛形を覚えることと、雛形に関連する知識を覚えることです。その後、令和7年度から平成20年度の過去問を何度も繰り返して知識を身につけることと、資料の読み方などを学んでください。これだけで合格するために必要な知識は十分身につきます。
令和7年度司法書士試験 今後の日程
- 令和7年8月12日(火)午後4時
法務省ホームページに筆記試験問題、多肢択一式問題の正解及び基準点が掲載されます。 - 令和7年10月2日(木)午後4時
筆記試験の結果発表等
筆記試験を実施した法務局又は地方法務局において、当該法務局又は地方法務局で受験した筆記試験の合格者の受験番号を掲示されます。
法務省ホームページにも、筆記試験の合格者の受験番号が掲載されます。 - 令和7年10月14日(火)
口述試験 - 令和7年11月4日(火)午後4時
最終合格発表
筆記試験を実施した法務局又は地方法務局(筆記試験免除者については、口述試験を実施した法務局)において、当該法務局又は地方法務局で受験した最終合格者の受験番号を掲示されます。法務省ホームページにも、最終合格者の受験番号が掲載されます。 - 令和7年11月28日(金)
官報への公告
令和7年11月28日(金)の官報に最終合格者の受験番号及び氏名が掲載されます。
- 関連記事:令和7年度 司法書士試験の日程
 | 山田 巨樹 講師 (司法書士・スタディング 司法書士講座 主任講師) 司法書士試験合格後、1998年から大手資格学校にて司法書士試験の受験指導を行う。その後、大手法律事務所勤務を経て独立し、東村山司法書士事務所を開設。2014年、「スタディング 司法書士講座」を開発。実務の実例を交えた解説がわかりやすいと好評。スタディング 司法書士講座では、長年の指導経験をもとに、短期合格のノウハウを提供している。 山田 巨樹講師の紹介はこちら |
司法書士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!
司法書士講座 無料お試し
- 短期合格の秘訣と講座活用法を解説!
- 講義、フルカラーWEBテキストを体験!
- スマホで解ける問題集、過去問集も
- 令和8年度受験生必見!法改正情報も解説!
勝ちパターンがわかる
PDF冊子もプレゼント中!


関連記事
司法書士になるには?受験資格、資格試験以外のルートも?- 司法書士の試験制度
- 司法書士試験の試験科目は?
- 司法書士試験の内容と配点は?
- 司法書士試験の合格率と試験の仕組み
- 司法書士試験合格に必要な勉強時間は?働きながら継続できる学習方法も解説
- 司法書士試験合格の近道は過去問?効果的な活用方法を紹介
- 司法書士試験独学合格を目指す勉強法3選
- 司法書士試験「民法」の攻略法
- 司法書士試験「不動産登記法」の攻略法
- 司法書士試験「会社法・商法・商業登記法」の攻略法
- 司法書士試験「マイナー科目」の攻略法
- 司法書士試験の願書の入手方法
- 司法書士試験当日の持ち物を確認しよう
- 司法書士口述試験の合格率は?落ちないって本当?
- 司法書士受験生が知っておきたい!民法改正の概要とは
- 他の司法書士に関する記事を読む
