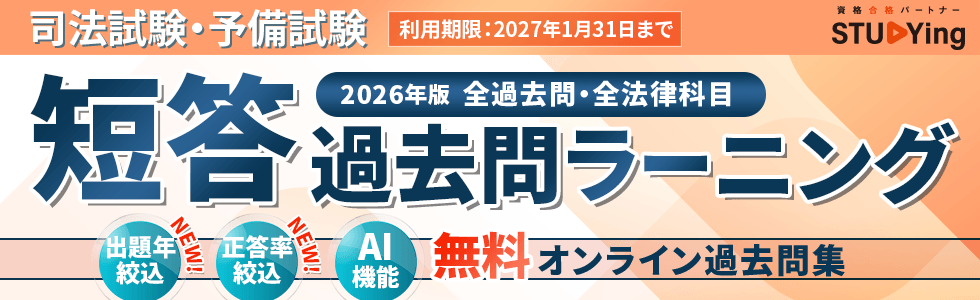取締役及び取締役会
司法試験平成26年 第43問
問題
解答・解説
解答:5
ア 正しい
イ 正しい
判例は、単なる名目的取締役に対しても招集通知を発しなければならないとしつつ、「取締役会の開催にあたり、取締役の一部の者に対する招集通知を欠くことにより、その招集手続に瑕疵があるときは、特段の事情のないかぎり、右瑕疵のある招集手続に基づいて開かれた取締役会の決議は無効になると解すべきであるが、この場合においても、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、右の瑕疵は決議の効力に影響がないものとして、決議は有効になる」としています(最判昭和44年12月2日)。
したがって、記述イは正しいといえます。
ウ 正しい
判例は、「定足数は、討議、議決の全過程を通じて維持されるべきであつて、開会の始めにみたされていればよいというものではない。けだし、法律は、一定数以上の取締役が会議に出席することを要請し、その協議と意見の交換により取締役の英知が結集されて一定の結論が生み出されることを期待しているものと解せられるからである。」としています(最判昭和41年8月26日)。
したがって、記述ウは正しいといえます。
エ 誤り
オ 誤り
判例は、362条4項が重要な業務執行についての決定を取締役会の決議事項と定めた理由は「代表取締役への権限の集中を抑制し、取締役相互の協議による結論に沿った業務の執行を確保することによって会社の利益を保護しようとする趣旨」としたうえで、「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、取締役会の決議を経ていないことを理由とする同取引の無効は、原則として会社のみが主張することができ、会社以外の者は、当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、これを主張することはできない」としています(最判平成21年4月17日)。
したがって、記述オは、無効主張の可否についての原則と例外を逆にしている点で、誤っています。