筋道を立てて考えること
2025/10/30
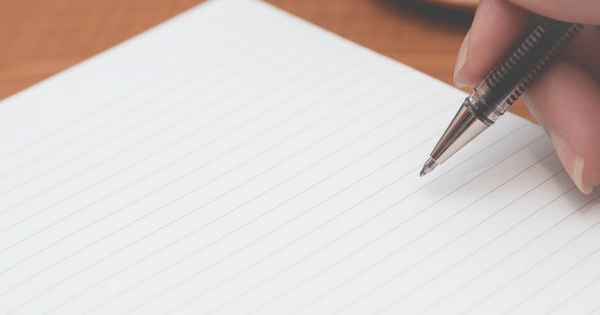
今回は分野こそ違えど技術士試験に役立つ参考書『古文研究法』(小西先生甚一著)から読解力向上に役立つと考える部分を紹介します。
技術士試験の学習を始めたとき、多くの人がまず戸惑うのは「何をどう勉強すればよいのか分からない」という点です。
数式のように答えが一つに決まるわけでもなく、問題文は抽象的で、どこに焦点を当てて書けばいいのかが掴みにくい。
この「掴みどころのなさ」こそが、多くの受験者が最初にぶつかる壁です。
小西甚一先生は『古文研究法』の「はじめに」で、国語という教科の学び方を次のように説いています。
「国語という学科は、一見するとつかみどころがないが、実はきわめて筋道を立てた勉強を要する学問である。」
これは、まさに技術士試験にもそのまま当てはまります。
技術士試験で問われているのは、「筋道を立てて考える力」です。
つまり、あいまいな課題を与えられても、論理的な筋を通して問題を整理し、構造的に説明できる力が求められています。
小西先生が「切れないナイフで固いビフテキをこすっているような解釈は、解釈とは呼べない」と述べたように、思考に筋が通っていなければ、どれほど知識を並べても理解には至りません。
技術士試験における論文作成も同様で、表面的な専門用語の羅列ではなく、筋の通った思考で課題を解き明かすことが評価されます。
小西先生が強調する「勉強に筋道を立てる」とは、思考を順序立てて積み重ねることを意味します。
技術士試験で言えば、次の三段階がその“筋道”です。
第一に、問題文を正確に読み取り、出題者の意図を把握すること。
第二に、課題を因果関係で整理し、なぜその課題が生じているのかを説明できるようにすること。
第三に、技術的対策と効果を明確に述べ、社会的意義と結びつけて論じること。
この三段階を一貫して行えば、どんな抽象的なテーマでも筋の通った論文に仕上がります。
小西先生はまた、「日本語で書かれているからといって、やさしいとは限らない」とも述べています。
技術士試験の問題文もまさに同じです。
表面上は日本語で書かれていますが、その背後には社会的背景、政策の方向性、技術的な含意など、複数の層が重なっています。
「だいたい分かったつもり」で読み進めると、論点を外してしまうのです。
出題者が求めているのは「正確な理解」であり、そこに到達できなければ論理がいくら立派でも評価は得られません。
小西先生が言う「方法論とは正しい筋道を立てることに尽きる」という言葉は、技術士試験の答案作成そのものです。
課題設定から原因分析、対策立案、効果検証までを一本の論理の筋で貫くことが、合格答案の条件です。
逆に、途中で論の方向がぶれたり、順序が逆になったりすると、どんな専門知識も説得力を失います。
筋を通すことこそが、技術者としての思考の基本です。
さらに小西先生は「古文の理解には三系統がある」として、「語学的理解」「精神的理解」「歴史的理解」を挙げました。
この考え方は、技術士試験にもそのまま応用できます。
つまり、
語学的理解=設問の構造を分析し、条件や制約を正確に読み取る力。
精神的理解=出題者の意図を推測し、課題の本質を見抜く洞察力。
歴史的理解=技術や社会の背景を踏まえて、課題の位置づけを理解する力。
この三つを組み合わせて問題を解釈することで、論文の軸がぶれなくなります。
小西先生は「富士山に登るのに、どの口から登っても目的は頂上に達することだ」と述べています。
技術士試験でも、専門分野の違いにかかわらず、最終的に目指す頂上は「技術を社会にどう生かすか」という一点にあります。
読解力とは、ただ文章を理解する力ではなく、問題文の裏にある社会的意図を読み取り、自分の専門性をそこに結びつける力のことなのです。
註:小西甚一(こにし じんいち、1915年〈大正4年〉8月22日 - 2007年〈平成19年〉5月26日)は、日本の文学者(日本中世文学、比較文学)。文学博士(東京文理科大学・論文博士・1954年)。筑波大学名誉教授。
古文研究法 (ちくま学芸文庫 コ 30-2)

| 匠 習作(たくみ しゅうさく) プロフィール
1962年生まれ。北海道函館市出身。本名は菊地孝仁。1988年より医療機器メーカーに勤務し、1991年20代で工場長に就任する。2014年までの23年間、医療機器製造工場の生産管理、人材育成、生産技術に携わる。2012年技術士機械部門、総合技術監理部門を同時に合格し、2016年に独立。 次世代のエンジニアを育てるべく、技術士試験対策講座を主催する。日本で初めてグループウェアを使った通信講座であり、分かりやすい解説、講師と受講者1対1を大事にする指導で人気講座となる。また、科学技術全般を、一般の人・子供向けに分かりやすく説明するサイエンスカフェなども自主開催。機械学会・失敗学会では、事故事例の研究などを行い、これも一般の人向けにセミナーなども開催している。 匠習作技術士事務所代表技術士 |
『講師匠習作の技術士応援ブログ』は、スタディング受講者様へお送りしたメールマガジンの内容をウェブ用に一部抜粋・編集して掲載しております。
今すぐ無料でお試し!
3大特典プレゼント!
まずは無料で体験!
特典1  合格ノウハウを公開! 受験生必見の合格セミナー さらに「必勝合格法」冊子付! | 特典2  論文対策のポイントを伝授! まずはここから!初めて論文対策をする方に手法を動画で紹介! | 特典3  添削課題のイメージがわかる! 添削課題(サンプル版)を無料で確認できる!有料版では16部門に対応! |
