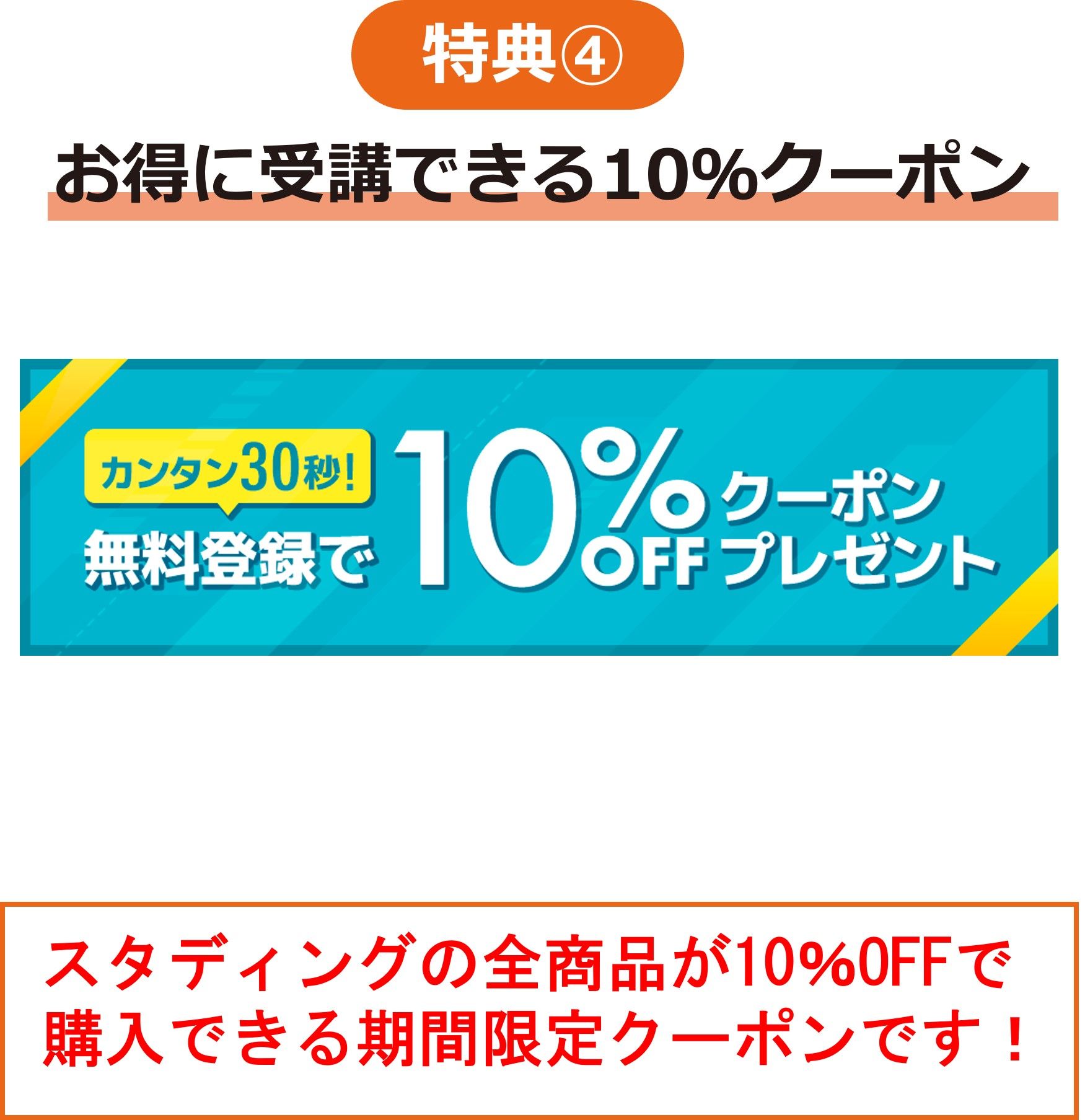弁理士合格者インタビュー
2022年度合格者インタビュー・体験談!
【インタビュー動画】はこちら↓

| お名前、合格された資格名、年度を教えてください。 |
|---|---|

|
佐藤拓也と申します。2022年度の弁理士試験に合格いたしました。
|

| 資格を取得したきっかけを教えてください。 |
|---|---|

| 現在は特許事務所に勤務していますが、以前はメーカーで開発の仕事をしていました。そのときに大学との共同研究に関わって社外の専門家と一緒に仕事をする機会があり、共同で特許出願することになったのですが、その際に弁理士の先生にお世話になりました。その経験を通して、私も弁理士の先生のような専門家として「社会に認められるような仕事がしたい」という思いが芽生えてきて、今までやってきた技術の経験を活かしながら専門家の道を目指そうと思って、弁理士の資格に興味を持ちました。 |

| スタディングを選んだ理由を教えてください。 |
|---|---|

| 元々理系の学校を出ていることもあり、電気系の資格は市販のテキストだけで何とか合格レベルにたどり着けました。しかし、弁理士試験の教材は、書店に行っても過去問集は出ているのですが、1から10まで教えてくれる本はありませんでした。また、弁理士試験の出題範囲は膨大なこともわかり、これは本だけで合格するのは無理だと思いました。そこで、動画で学べるスタディングを選びました。スタディングで学習することは、独学で本を買って勉強することに比べたら雲泥の差があると思いますね。
|

| スタディングの講座の良いところを教えて下さい。 |
|---|---|

| 広島県(地方)に住んでいるため、大手予備校に通学することはまず無理でしたので、 自分に一番合ってる学習方法はオンラインでスマホを使って学習することかなと思っていました。勉強は2019年に始めたのですが、その後は感染予防の観点から外出が難しくなって、そのときにスマホで学習するスタディングを選んでよかったなと思いました。スマホでの学習なら感染対策の影響を受けずに、自分のペースでどんどん学習を進めていけたので 、そういった点ではすごく良かったと思います。 |

| 便利だった機能はありますか? |
|---|---|

| 機能の点として良かったところは、再生スピードを自分で自由に変えられるところです(僕が一番やりやすかったのは1.5倍速)。それを何回も回すことで、最初わからないなっていうところも、段々とわかってくるようになりました。スタディングの講義を何回も繰り返すことで短答はもちろん論文試験だったり、そのあとの口述試験にも通じるような知識がすごく身に付いていきました。口述試験対策で初めて大手予備校の大阪まで行ったのですが、受けたときに「知識量が十分にある」という評価をいただいたので、スタディングの学習で大手予備校を受けている人に引けを取らないぐらいの知識量は手に入れられていると実感しました。 |

| 講義の内容はいかがでしたか? |
|---|---|

| 今までずっと理系の道を進んできたので、法律の勉強はしたことがない全くの初学者っていう状態で始めました。そんな私でも講義の内容はものすごくわかりやすく、講義で出てくるスライドも簡潔にまとめられていたので、動画を見ていくだけで「ここがわからない」と引っかかることなく最後まで流すことができました。スタディングの講義は全体を通してわかりやすくて、声も聞き取りやすいので音声だけにして車での移動中だったり通勤中の歩いてるときに聞いたりすることもできるので、生活の全てが弁理士試験の勉強になるイメージで学習できる点が良かったですね。 |

| 紙のテキストは使いましたか? |
|---|---|

| 家でずっと勉強するよりはカフェに行ったり、歩きながらだったり、どこか自分の好きなところに行って色んな場所を移動しながら勉強するタイプでした。紙のテキストだとすごく重くて持ち歩くのも一苦労だと思いますが、私の場合はスタディングの教材をスマホ一つあればどこでもできたので、紙のテキストはいりませんでした。 |

| 勉強時間はどのくらいでしたか? |
|---|---|

| 勉強時間はアプリで管理していたのですが、トータル約2,500時間使いました。平日は通勤時間、昼の休憩時間、帰宅してからの時間を使い2時間、多くて3時間ぐらいでした。休日はずっと勉強詰めだとモチベーションが下がってくるので、土曜日の半日は妻と出かけたり友達と遊んだり、そういったことに使って残りの時間を全て勉強に充てていました。休日でだいたい1日5時間程度、直前期には6~7時間ほどは勉強していました。 |

| スキマ時間を使った勉強法について教えてください |
|---|---|

| まずは通勤時間を活用しました。家から駅まで徒歩15分、電車に乗って20分、駅から会社まで徒歩15分かけて通勤しているのですが、まず歩いてるときは音声で講義を聞く、電車に乗っているときは音声と動画を見て講義を聞く、駅から会社に歩くときは、また音声で講義を聞いていました。また、例えば買い物に行ったりするときも車のオーディオに繋いで講義を音声で流したりしていました。これらは全てスマホでできるので、混雑していて本を開くことがなかなか難しい場所・時でも講義を進めることができました。色んなスキマ時間を勉強に充てられたので、1日の勉強量で言うとプラス1時間ぐらいはされていたのかなと思います。 |

| 自宅や通勤時間以外ではどこで勉強していましたか? |
|---|---|

| 色んなところで勉強するのが好きなので、ショッピングセンターに行ってベンチでテキストを開いたり、子どもや親子連れが遊んでる公園に行ってベンチに座って勉強したり、カフェにもよく行くのでカフェで勉強したり、図書館に行ったり、午前と午後で場所を変えたり、単元ごとに場所を変えたり、色んなところを転々としながら勉強してましたね。 |

| 論文対策をどのように始めましたか? |
|---|---|

| 短答式の勉強が一通り済んだところで、論文式の勉強を始めました。始めた当初は、過去問をサラサラっとめくってみても何を書いたらいいのかそれすら全くわからない状態からのスタートでしたので、スタディングの教材でまずは型を覚えることに専念しました。講義を聞いてから練習問題を答えを見ながら写経してみる、それを繰り返して2周目になったら、今度は自分でその答えを見ずに解いてみる。 スタディングの「論文対策講座」で出題される例題と練習問題は、過去問の一部だけを抜粋した内容になっているので、いきなり初心者が本試験レベルの過去問を解くことは無理だと思うところ「この文量なら初めてでも最後まで書き終える」ことができました。 このようにして論文の型を身に付けることができました。この状態にしてから、本試験レベルの過去問にチャレンジしたので、スムーズに学習を進めることができたと思っています。 |

| 答案の添削は受けましたか? |
|---|---|

| 私は一度も添削をしてもらったことがなくて、スタディングの教材で型を覚えて、その型に従って問題を解いていくやり方でした。スタディングの教材には模範答案がついているので、模範答案に近づけるように自分で「模範答案とちょっとずれてるな」というところは修正して、それを繰り返していきました。結果的には、添削に頼らなくても、合格レベルの答案を書けるようになったので、添削があればいいかもしれないですが、スタディングの教材なら添削がなくても合格はできると思います。 |

| 答案構成のトレーニング法について教えてください? |
|---|---|

| 答案構成が20分でできればあとは書くだけなので、まずは全文書きをするよりは答案構成を時間内にきっちりする訓練をしました。伊藤先生がおっしゃっていた答案構成と全文書きの中間あたりの答案を書いてみて、最後は確認程度に1時間で全文書きをしてみる、そういった学習をして1時間で1.5枚の答案用紙を書くことができるような訓練をしました。 構成を考えるときに、スタディングの「頻出15パターン」を何回か繰り返してると、例えば「この問題は措置対応パターンだな」「この問題は規定説明パターンだ」と、そういったのが頭の中にぱっと浮かんでくる、その短い時間を使ってどう変えたらいいかを訓練しているので、答案構成をどういうふうに構成したらいいか、わからないことはあまりなかったですね。 |

| モチベーションを保つコツはありますか? |
|---|---|

| 論文は人によってはなかなか通らなくて、そうこうしているうちに短答式の免除が切れてしまって、どんどん時間が経てば経つほど試験に疲れて、試験に飽きてきてモチベーションが下がっていくことになります。ですので、短期間で合格することが重要になります。 まずは、勉強を始めることはすごく億劫なことなので、始めるハードルを下げてみる。例えば、勉強場所を変えてみるとか、どうしてもやる気が出ないときはYouTubeをテレビに繋いで好きな動画を流し見しながらながら勉強したりとか、とにかくどういった形でも始めてしまう、そういった色んな工夫をすることでモチベーションを下げずに勉強へのハードルもぐんと下げて、楽しく勉強することは意識してましたね。楽しいうちに合格してしまうのがコツだと思います。 |

| どんな人にスタディングをおすすめしますか? |
|---|---|

| 弁理士の資格に興味があるけれど、本当にそれが自分にとって合ってるかどうかわからない人、予備校の費用が高くて弁理士試験の勉強を始めることに躊躇している人、そういった方にとって、スタディングは気軽に始めることができるので、始めてみて弁理士試験が自分に合ってるなと思えばそのまま突き進んで、ちょっと違うなと思ったら撤退することもできます。 また、地方に住んでる方にも非常にお薦めできます。大手予備校の利益が享受できるのは、通学して先生の生の講義を聞くことなので、東京や大阪に住んでいないとなかなかそのメリットを享受できないところですが、スタディングは完全オンラインで勉強できるので、地方に住んでる人でも学習を始めやすいと思います。 |

| 論文式試験を突破したい人にメッセージをお願いします |
|---|---|

| 論文式試験に合格するために必要な知識や解き方は、スタディングで十分に身につけられるので、あとは自分との戦いですね。いかに勉強時間を確保して進めることができるか、例え高いお金を払って予備校に行っていたとしても、完全に予備校のペースに任せきりにして自発的に勉強しなかったら合格は到底できないでしょう。論文式試験の合格に必要な知識とノウハウはスタディングで習得できるので、不安を持つことなく突き進んでいただけたらなと思います。 |
| すべての合格者の声を見る |