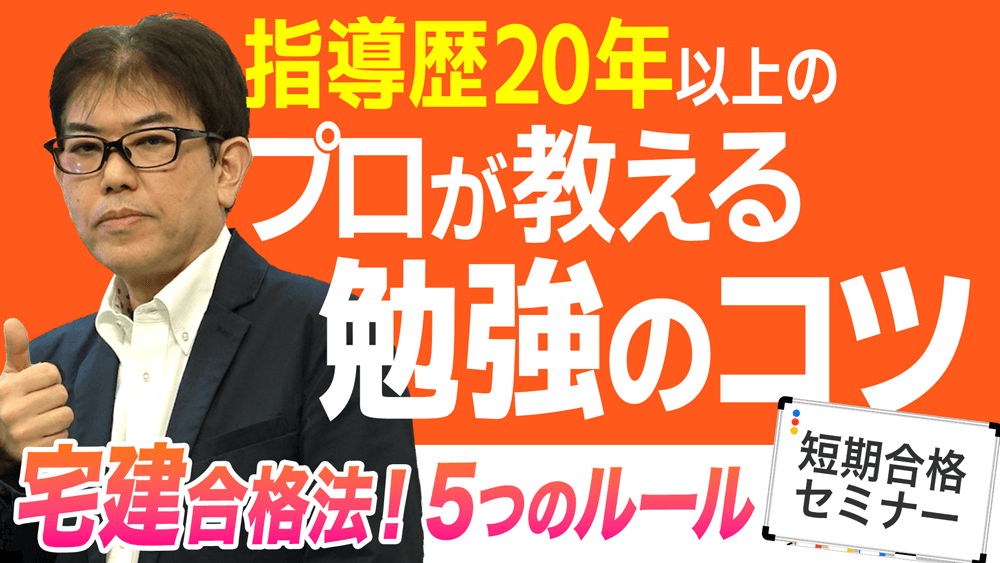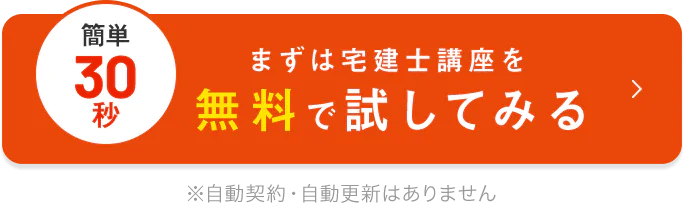権利関係-債務不履行
平成22年 第6問
宅建士試験ピックアップ過去問解説
問題
両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
2 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
3 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
解答・解説
解答:3
1 誤り。
通常生ずべき損害については、当事者が予見又は予見可能であるかにかかわらず、賠償請求できます。
2 誤り。
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を「予見し、又は予見することができたとき」に限り、債権者は、賠償請求できます。なお、この場合の当事者とは、債務者の意味します(判例)。
3 正しい。
債務不履行による損害賠償請求権は、本来の履行請求権と同一性を有するので、その消滅時効は、本来の債務の履行を請求することができる時から進行します(判例)。
4 誤り。
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、必ず債権者の過失を考慮しなければなりません。なお、不法行為の場合には、債権者の過失を考慮することができるので、混同しないように注意が必要です。
ポイント 債務不履行による損害賠償の範囲
・通常生じる損害(通常損害)については、債権者は、債務者が予見又は予見可能であるかにかかわらず、請求できる。
・特別の事情によって生じた損害(特別損害)については、債権者は、債務者がその事情を予見し、又は予見することができたときに限り、請求できる。
学習するには
権利関係7-売買契約1
<2025年度試験対策>
今から始める方へのおすすめコース

|
宅建士合格コース[2025年度試験対応]一括 14,960円~29,800円
「コンプリート」「スタンダード」「ミニマム」の3つのコースタイプから選べる! |
| 講座一覧を見る・受講する |