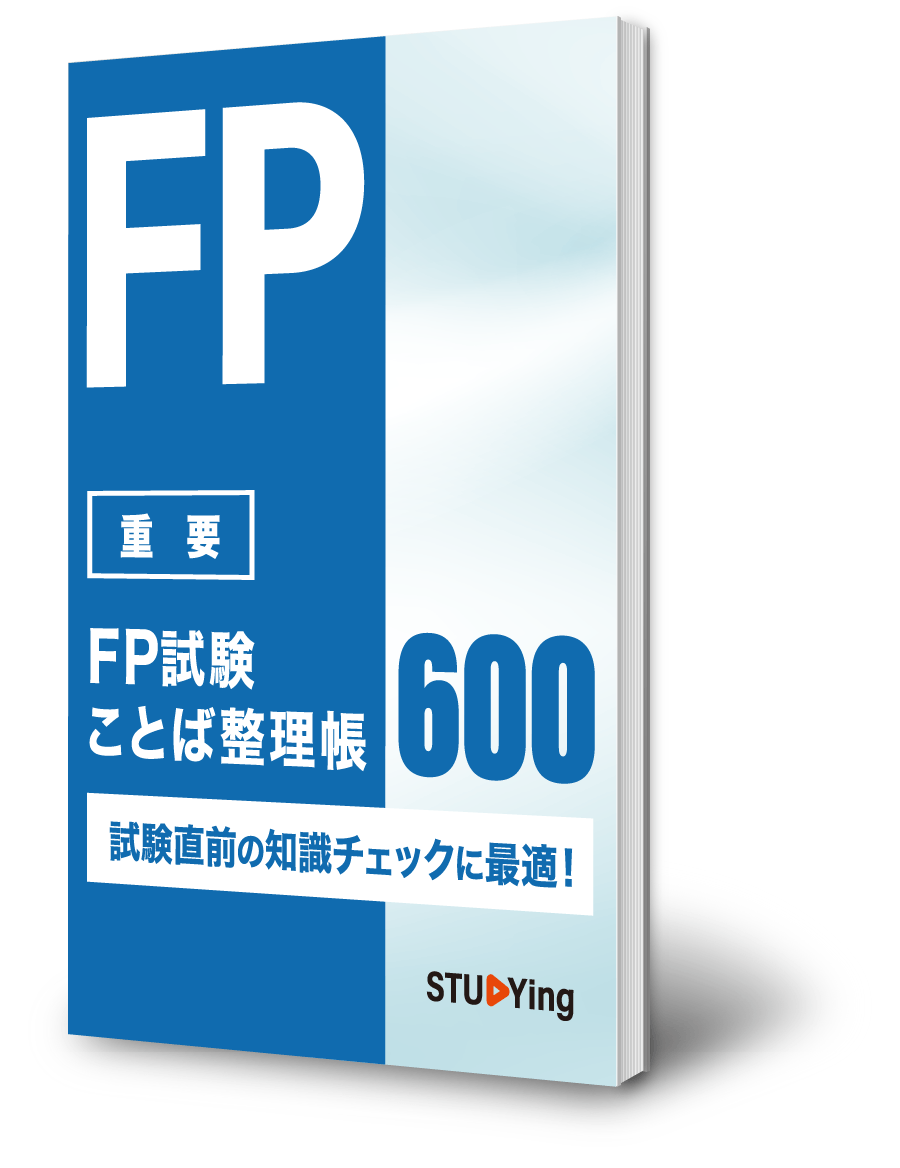金融資産運用-投資信託の運用手法等
2020年1月学科第22問
問題
投資信託の一般的な運用手法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- マクロ的な環境要因等を基に国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率に応じて、個別銘柄を組み入れてポートフォリオを構築する手法をトップダウン・アプローチという。
- 各銘柄の投資指標の分析や企業業績などのリサーチによって銘柄を選定し、その積上げによってポートフォリオを構築する手法をボトムアップ・アプローチという。
- ベンチマークの動きにできる限り連動することで、同等の運用収益率を得ることを目指すパッシブ運用は、アクティブ運用に比べて運用コストを低めに抑えられる傾向がある。
- 企業の将来の売上高や利益の成長性が市場平均よりも高い銘柄を組み入れて運用するグロース運用は、配当利回りの高い銘柄中心のポートフォリオとなる傾向がある。
解答・解説
解答:4
金融資産運用から、投資信託の運用手法等に関する問題です。
2級FP試験(学科)では、投資信託の運用スタイルに関する問題は定番問題といえます。
特にアクティブ運用とパッシブ運用を中心に、運用スタイルによる分類は確実におさえておきましょう。
【アクティブ運用とパッシブ運用】
・アクティブ運用(アクティブ型投資信託)
アクティブ運用とは、日経平均やTOPIX等のようなベンチマークと呼ばれる指標を上回る運用を目標にしている運用スタイルです。
・パッシブ運用
パッシブ運用とは、ベンチマークの値動きに忠実に連動することを目的としている運用スタイルです。
代表的なものとして、インデックス運用があります。
パッシブ運用は、ベンチマークの値動きに連動することを目的としているため、たとえば日経平均株価に連動するパッシブ運用をするならば、日経平均の銘柄を全て買えば同じ値動きをする訳です。
しかし、アクティブ運用は、ベンチマークの実績よりも上回ることを目的としなければならないので、運用実績を上げるために様々な手法が取られます。
また、具体的な銘柄選択の手順・手法として「トップダウンアプローチ」と「ボトムアップアプローチ」に分かれ、銘柄選択の組入れ基準として「バリュー投資」と「グロース投資」という考え方に分けることができます。
【運用スタイルによる分類】

(選択肢1)適切
トップダウン・アプローチとは、国や地域の経済・金利・為替などのマクロ経済動向の予測をもとに、資産や業種別の配分を決め、その後個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築する運用手法です。
(選択肢2)適切
ボトムアップ・アプローチとは、トップダウン・アプローチとは異なり、個別銘柄の投資指標の分析、企業業績などのリサーチにより銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する運用手法です。
(選択肢3)適切
パッシブ運用は、ベンチマーク(株価指数など)の動きにできるだけ連動することにより、ベンチマークと同等の運用収益率を得ることを目指す運用スタイルです。アクティブ運用より銘柄の売買回数が比較的少ないことから、アクティブ運用に比べて運用コストを低めに抑えられる傾向があります。
(選択肢4)不適切
グロース投資(グロース運用)は、企業の将来の売上高や利益の成長性が高い銘柄を組み入れて運用する投資手法です。成長性の高い銘柄の場合、一般的に、利益が出ても、配当より将来の事業のために投資することが多いため、配当利回りの低い銘柄中心のポートフォリオとなる傾向があります。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
学習するには
「3-2 投資信託」 投資信託の分類・商品の特徴
オンラインFP講座を、今すぐ無料でお試しできます!
FP講座 無料お試し
- FP検定の傾向と対策が分かる無料セミナー
- 手元に参考書がなくても勉強が始められます!
- 3級・2級の動画講義と問題演習を体験!
- 本試験を想定した過去問集も試せる!
PDF冊子を無料プレゼント!